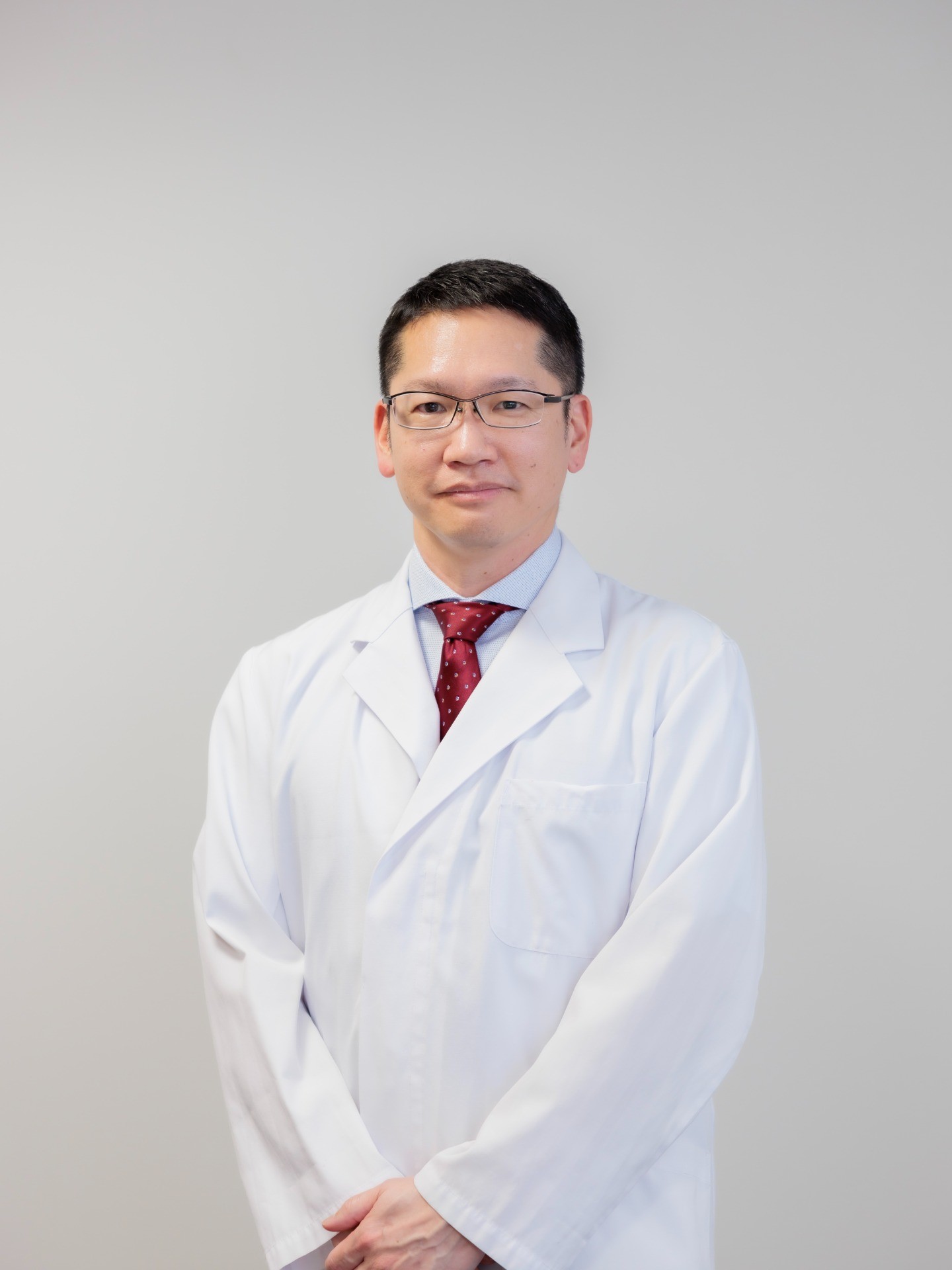
柴田 弘太郎ロバーツ
しばた こうたろうろばーつ
| 役職 | 部長 兼 リハビリテーション科部長 |
|---|---|
| 専門分野 | 関節外科(股・肩・膝)、スポーツ外傷 |
| 資格 | 日本整形外科学会(専門医) |

人間が人間たる所以は、高度な知能とそれを支える高機能の運動能力を持ち合わせていることです。また、人間は二足運動をすることで体の代謝や循環のバランスを保ち健康を維持しています。怪我や変形疾患等でその運動能力が損なわれると、健康を維持することも困難になります。その高機能の運動能力を再建し回復させ治療をする科として、整形外科は大切な役割を果たしています。皆さまのお役に立てるよう大阪府済生会野江病院 整形外科チームは日々努力し精進しています。
整形外科は、四肢と脊椎の骨、関節、筋肉、神経などの病気やけがによる損傷を治療する科です。整形外科で扱う病気は、加齢によって起こる変性疾患、スポーツや事故による外傷疾患、感染性疾患、骨・軟部腫瘍や転移性腫瘍による疾患、小児の先天性疾患、成長に伴い発生する疾患等多岐にわたります。さらに超高齢化社会となり、骨粗鬆症を含め運動器疾患の治療の重要性は増しています。
当院は急性期病院であり、保存的治療で改善しない患者さんに対して、手術を行うことを主として診療に当たっています。現在、各分野の専門医が常勤医として在籍しており、協力体制で治療を行っています。非専門分野の高度な疾患については、京都大学系列のみならず、地域の専門病院を紹介、または専門医を当院に招聘することで、専門性高い医療を受けられるよう連携しています。また、急性期を過ぎて慢性化した患者さんは、治療を周辺のリハビリ専門病院にお願いし、地域医療連携を行っています。
※原則予約制のため、紹介状をお持ちください。
→股関節鏡手術
→人工股関節置換術(THA)
→人工股関節再置換術
→骨温存手術
→ 脊椎内視鏡手術や脊髄髄内腫瘍手術以外、頚椎から骨盤まで低侵襲前方固定法OLIF (Oblique Lateral Interbody Fusion、オーリフ)を含めた固定術および除圧術などあらゆる脊椎脊髄手術を施行
→鏡視下半月板切除術、鏡視下半月板縫合術、鏡視下前・後十字靭帯再建術、鏡視下滑膜切除術、鏡視下関節内遊離体摘出術、鏡視下ドリリング、モザイクプラスティ、自家培養軟骨移植
→関節温存手術(骨切り手術、軟骨移植術)、人口膝関節置換術(TKA)
→鏡視下腱板修復術、鏡視下バンカート修復術、鏡視下上方関節唇・靭帯修復術、鏡視下肩関節授動術(関節包切離術)、鏡視下上方関節包再建術(大腿筋膜移植術)、人工骨頭置換術・人工肩関節置換術(リバースショルダーを含む)
→観血的骨接合術、創固定術、経皮的鋼線刺入術
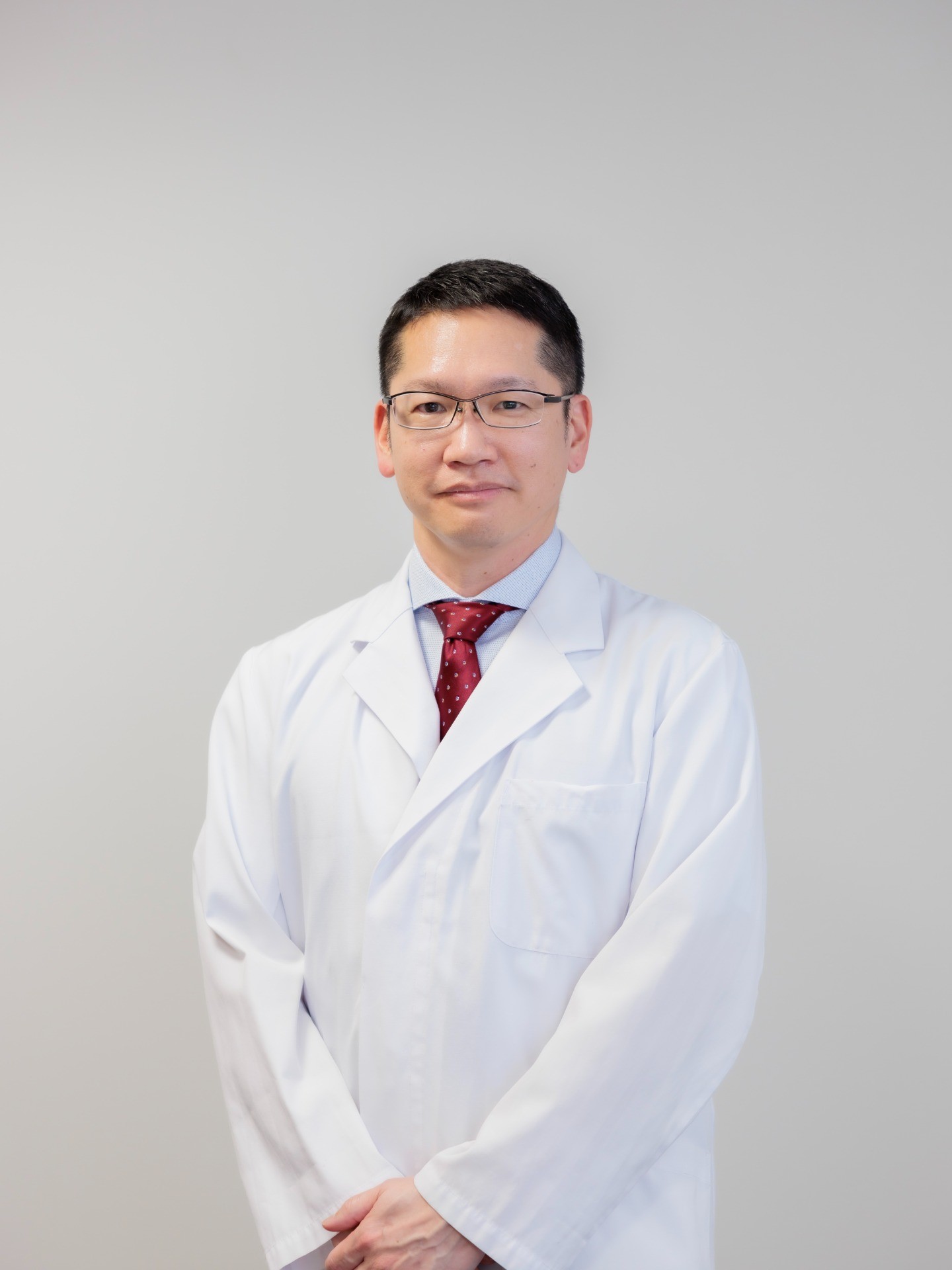
柴田 弘太郎ロバーツ
しばた こうたろうろばーつ
| 役職 | 部長 兼 リハビリテーション科部長 |
|---|---|
| 専門分野 | 関節外科(股・肩・膝)、スポーツ外傷 |
| 資格 | 日本整形外科学会(専門医) |
石井 達也
いしい たつや
| 役職 | 副部長 |
|---|---|
| 専門分野 | 脊椎外科 |
| 資格 | 日本整形外科学会(専門医・脊椎脊髄病医) |
大島 卓也
おおしま たくや
| 役職 | 医長 |
|---|---|
| 専門分野 | 整形外科一般、外傷整形外科、膝関節外科 |
| 資格 | 日本整形外科学会(専門医) |
田吹 紀雄
たぶき のりお
| 役職 | 医員 |
|---|---|
| 専門分野 | 整形外科一般、外傷整形外科 |
| 資格 | 日本整形外科学会(専門医・リハビリ認定医) |
樋 謙作
かけひ けんさく
| 役職 | 医員 |
|---|---|
| 資格 | 日本整形外科学会(専門医) |
増井 伸祥
ますい のぶよし
| 役職 | 医員 |
|---|
吉岡 侑真
よしおか ゆうま
| 役職 | 医員 |
|---|
寺岡 佳亮
てらおか けいすけ
| 役職 | 医員 |
|---|
(単位:件)
| 脊椎外科 | 頚椎 | 26 |
|---|---|---|
| 胸腰椎 | 104 | |
| 関節外科 | 人工股関節 | 41 |
| 人工股関節再置換 | 5 | |
| 股関節鏡手術 | 11 | |
| 大腿骨人工骨頭 | 69 | |
| 人工膝関節 | 54 | |
| 膝半月板手術 | 30 | |
| 膝靭帯再建術 | 6 | |
| 下肢骨切り術 | 4 | |
| 肩関節鏡 | 10 | |
| 人工肩関節 | 10 | |
| 外傷 | 上肢骨折手術 | 145 |
| 下肢骨折手術 | 152 | |
| 手の外科 | 30 | |
| 腫瘍外科 | 3 | |
| その他 | ||
| 合計 | 823 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | B-5 | 予約外来 石井 |
予約外来 柴田 |
予約外来 田吹 |
予約外来 大島 |
予約外来 柴田 |
| B-6 | 予約外来 大島 |
予約外来 田吹 |
予約外来 泰永 (第2・4) |
予約外来 樋 |
予約外来 吉岡 |
|
| B-4 | 予約外来 樋 |
予約外来 |
予約外来 増井 |
予約外来 石井 |
||
| 午後 | B-5 | 手術 | 予約外来 柴田 |
手術 | 検査 | 手術 |
| B-6 | 検査 | |||||
| B-4 | ||||||
※整形外科の診察は原則予約制です。 紹介状をお持ちの方はこの限りではありません。
